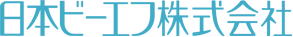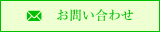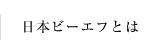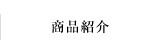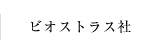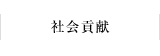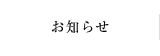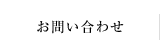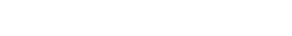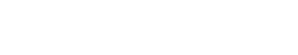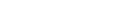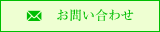129 アルツハイマーじゃないよ
- 効果があるかどうか疑問に思った薬はおそらく無効である。
- 投薬を中止して患者の状態が悪くなる様な薬はほとんどない。
これは医師のバイブルといわれている「ドクタ-ズルール425」の一文
私たちは認知症の事をアルツハイマーとひと言でかたづけてしまいがちです。
しかし認知症には大きく分けて3タイプあるようです。
アルツハイマー症 忘れっぽい、穏やか、いわゆる可愛らしいお爺ちゃん、お婆ちゃんタイプ
ピック症 記憶は良い、すぐ怒る、行動異常がある
レビー症 元気ない、鬱、幻覚を見る、寝言が多い
もっとも大切なことは患者がどのタイプに属しているかを医師が見極める事。
見極められずに投与すると、例えばすぐ怒る患者(ピック症)に元気になる薬(レビー症)を投与したら・・・、結果は明らかですね。
医師の誤った判断からこのような投与が行われている事が多いのには驚かされます。
それがわかるのはある期間の投与が行われた結果を見ての事。
ただただ信じて摂り続ける無抵抗の私たちはたまったものではありません。
「ひと目みただけでどの認知症タイプかわかる事も多い。」
「他院で投与された薬を半分にするだけで改善する事も多い。」
「薬を変えることによって車椅子だった患者が歩けるようになった。」
日本ビーエフの勉強会では市川フォレストクリニック 松野院長がこうお話されていました。
このような医師が増えていく事が健康寿命を延ばしていくことになると思います。
加齢と共に脳機能が衰えていくのはしかたがないこと。
それはしわが増えたり、運動機能が衰えたりすることと同じ事。
しかし薬による悪化からは絶対に避けたいものです。
- 患者には病人になる方法を教えるのではなく、健康になる方法を教えなさい。
こんな文もドクターズルールでは教示しています。
128 ひとりでも人に話せばうわさが広まるのは覚悟しよう
ひとりでも人に話せばうわさが広まるのは覚悟しよう
ちょっと脅しているようなこの文章はある小冊子の中の「心得」の筆頭にくる文章です。
何の冊子でしょうか?
・・・・・・これは、高額宝くじ当選者だけが手にする小冊子です。
「子孫のために美田残さず」
これはかの西郷隆盛の言葉です。
そして次は世界的な大富豪ウオーレンバフェットさんが言ったことです。
「ある程度のお金が自由になったら次の順序で投資してください。」
1 健 康
2 ス キ ル
3 ビジネス
4 人間関係
5 資 産
大富豪なのに第一番に健康を挙げているところが興味深いですね。
あらゆるジャンルの成功者たちが口をそろえて言うことは「時間の貴さ」。
その大切な時間とお金を まず健康に投資すべきと言っています。
そして次に仕事のためのスキルに投資していていく。
健康とスキルはたとえ破産してもなくなることはありません。
この1から5の順序を間違えると間違った人生を歩んでしまうのでしょうか。
高額宝くじ当選者の7割は破産している。(米国)
NBAバスケットのミリオネヤプレイヤーの6割は悲惨な末路を迎えている。
大金を手に幸せのはずがこうなってしまうのは、まずはじめに5番目の資産を手に入れてしまうから?
健康やスキルがない人が資産を手に入れると人間関係が壊れてしまいそうです。
健康が大事なのは大富豪ならずともわかります。
しかし忙しい日々の生活のなかにあって第一に持ってくるのは難しいことですね。
おいしいけどからだによくないものは避け、時間を割いて運動を続けるのは大変なこと。
それでもまず、健康に投資してみませんか。
127 あー、もっと鍛えればよかった
これは「リタイヤ前にやるべきだったこと」のアンケートでもっとも多かった回答です。
回答者は55~74歳の男女1060人。
それもそのはず日本人の健康意識は34か国中34位(OECD調査)
「健康管理は何もしない」が46%にもなり、世界一医療に依存する自己責任が乏しい。
厚生労働省はこんな日本人の一面をのぞかせていると言います。
WHO(世界保健機構)が日常に必要な医薬品として定めた薬は約300種類。(必須医薬品)
それに対して日本の薬の種類は世界トップレベルの1万7000種に達するようです。
日本は世界全体の約6分の1もの薬を消費する医薬品消費国なのです。
北海道夕張市が財政破綻した時に私立病院がなくなり街から救急病院が消えてしまった。
高齢化45%の夕張市の医療体制が心配されました。
そんな中、死亡率、医療費、救急車の搬送回数すべてが下がってしまいました。
「自分でやらなきゃ」そんな意識が芽生えたのでしょうか。
自己責任とは自分の行動を意識し、よい方向にコントロールすることに他ありません。
自身をより向上させるのは技能や知識ではなく、意識を向上させることのようです。
街の一角でレンガを積んでいる職人さんに聞きました。
「なんでレンガを積んでいるの?」-「今日中にあそこまで積まなきゃいけないのさ。」
違う職人さんに聞くと、 ---「ここに教会の壁を作っているのさ」
さらに違う職人さんに聞くと、---「街のみんなを幸せにするための教会を作っているのさ」
まったく同じ作業をしているのにこの目的意識の違いは建物に大きな違いを生みます。
世界23カ国28,000人を対象とした意識調査で「健康で最も気にしていることは?」
1十分な睡眠をとる
2健康的な食生活
3定期的な運動
わかっているなら「まず やってみよう」という意識。
これがないと一歩も前へ進みませんね。
128 日本の文化
日本の文化
女性の足腰が昔と比べて弱くなったのには理由があります。
運動不足やダイエット信奉だけではない。
と話していたのは某バス・トイレメーカーの開発者。
話者がこの業界の人ですから理由はおわかりでしょうか?
これは、女性は野球のキャッチャーのようなトレーニングを毎日欠かさず行っていたからです。
男性の場合はせいぜい1日1~2回、でも女性の場合は7~8回。
長いトレーニングの場合は15分以上。
足が太くはなりますが、逞しく強い足腰になるのは当然ですね。
現在では、あの姿勢すら取れない若者が大勢いるのには驚きです。
足裏マッサージ、竹踏み、足湯、突起サンダル・・・・・。
足裏には健康のためのつぼが多く存在しているようです。
西洋人が靴を履いている時代でも日本人はわらじで日本列島を歩き回っていました。
わらの感触と相まってとてもよい刺激を体中に送っていたのかもしれませんね。
コペンハーゲンの大学教授が10年かけて25カ国でこんな実験を行いました。
靴を履かない教室 Shoeless Environment School
靴を履かずに授業や休み時間を教室で過ごすとどうなるかという実験です。
その結果、児童たちの落ち着きは増し、登校時間が早く、帰宅は遅くなったといいます。
学びへの姿勢が向上し、教室内の雑音が減り、より勉強をするようになったというのです。
「椅子」は人間工学的には座って姿勢を楽に保ち、身体への負担を減らす道具です。
ですが本来は外の世界と内の世界を分ける心理的な境界線として誕生いたしました。
境界線は塀や家の壁ではなく椅子だったんですね。
靴を脱がない西洋では、椅子は我が家に戻ってホッとする瞬間を作るものでした。
椅子の文化の無かった日本はわらじを脱いだ瞬間が椅子に座った時に匹敵いたします。
そんな状態で勉強すれば気持ちも和らいで落ち着き、はかどるのかも知れませんね。
ビオストラスもそんな状態のときに摂るとよりよいかもしれません。
127 隣の芝生はよく見える
隣の芝生はよく見える
公園で元気に遊ぶ小学生をあまり見かけなくなりましたね。
たまに見かけるとベンチに座ってゲームをしている。
電車に乗っている高校生も話さずお互いにメールなどに熱中している風景をよく見かけます。
人間関係がどんどん希薄になっています。
そのせいか近頃の新入社員は電話を取りたがらないという。
どこの誰からかかってきた電話かわからないのは怖く、恥ずかしいらしい。
それでいて自分の日常をネットに投稿することには余念がない。
ネット上やメールで話せるから直接対話をしなくなったのでしょうか。
直接対話をしたくないからメールに頼るのでしょうか、よくわかりませんが、
こんな若者達の将来を懸念してか このような実験が行われました。
コペンハーゲンの大学で1100人のSNSに夢中な若者を2つのグループに分け、一方に対してSNSを1週間禁止してみました。(SNS:社会的なつながりをネット上で行えるサービス)
どんな結果が生まれたでしょうか・・・?
すると効果てきめんで日常に対しての満足感が高いレベルまで達したというのです。
怒りやイライラが消え、自分の仕事への注力や社会性が増してきたといいます。
そして孤独感が消えてきたそうです。
SNSで大勢の友達と毎日のように対話していたのに孤独だったのでしょうか?
Facebook envy(フェースブックの妬み)という言葉が流行のようです。
友人の投稿を見ると何でもないことなのに幸せや成功しているように感じて妬んでしまう。
実際はたいしたことないのに相手のちょっとしたことを拡大解釈して落ち込んでいくらしい。
隣の芝生だったら近寄って見て「そうか、どこも同じだ」と体感することができますね。
でもネットの場合にはそれができずどんどん鬱積していきます。
特にSNSに多く加入している人は鬱になるリスクが数倍も高いといっています。
大人の義務として 子供たちには最小限で済ませ、実体験を多くさせたいものですね。
126 三つ子の魂100まで とはいいますが・・・、
三つ子の魂100まで とはいいますが・・・、
・アメリカの乳児は泣きごとを言うことをためらうようです(小学生ではなく乳児 です)。
これはこの国の文化が消極的な行いをよいことと認めないから。
・ポーランドの乳児は悲しいときの表情が豊かだそうです。
これはショパンを生んだこの国の気質が感情や感覚を大切にする文化があるから。
・チリの乳児はエネルギッシュ、そしてトラブルと奮闘するそうです。
これはかの暑い国、南米の母親達の活気ある振る舞いに接しているからだそう。
・韓国の乳児は長い間動かず集中することができるようです。
これはアジアのある地域では自制心に価値を置くことからくるようです。
これらは世界23カ国で5年間 生後わずか6ヶ月から12ヶ月の乳児の調査結果です。
一部はヨーロピアンジャーナルで発達心理学の見地から発表されています。
それぞれの情景も浮かび、「ウン、ウン なんとなくわかる」とうなずけますね。
しかし「環境や文化よりも血筋では?」とも思っていると、こんな研究も行われていました。
ニュージランドの大学をベースに1000人を超える世界中の3歳児が調査されました。
「おはなしと運動」を中心に、忍耐力、落ち着き、性急さなどのポイントをつけていきます。
大人になった35年後に再調査するという大がかりな調査の結果・・・・。
ポイントの低かった幼児たちは成長した後、問題を抱えていた割合がとても高かったそうです。
有罪になった人、処方箋の常用者、病気の傾向がある人、異常な飲酒喫煙者・・・。
この大人たちは幼児期に適切な脳への刺激を与えられなかったと解説しています。
誰からもそのためのサポートが得られず脳の発達が遅れ、問題に対処する能力が育たなかった。
逆を言えば、このような調査を全幼児に行いサポートしていけば、その後の人生もずいぶん良くなっていくだろうと研究者は言葉を締めています。
環境や文化そして脳への刺激、睡眠、運動、栄養、考え過ぎると子育てが怖くなってきますね。
でも 最も大切なのは自分が愛されていることを心の底から感じさせてあげることでしょうか。
ビオストラスは子供の情緒の安定、動作、集中力の向上にも多くの効果を生んでいます。
残念だったのはこの調査で日本の乳児の調査がなかったことでしょうか。
ただ、2割もの0歳児がスマホやタブレットを触ったことがあると最近発表されていました。
125 太らない食べ方
さあ、こうすれば太りません。
あのモデルさんもやっているそうです。
実践しましょう。
ご飯はいくら食べても午前中ならOK。
1日の食事の時間が8時間以内ならどれだけ食べても大丈夫。
食べる順番を変えると太りにくい。
肉は食べても太らない。赤み肉なら特によい。
冷や飯を食べると脂肪が燃焼する。
お米はパンや麺類より消化吸収率が高く太りにくい。
おでんは高タンパク低カロリーで太らない
全粒粉のパンは血糖値が上がりにくいから太らない。
砂糖と油物は一緒にとったらダメ。
お酒ならワインがよい。
マヨネーズはノンオイル。
大豆はおなかいっぱい食べてもふとらない。
イカ、するめは動物性タンパク質だけど低カロリー。
甘いものを断ちすぎるとストレスがたまるから和菓子がいい。
ラーメンにはねぎを多めに入れれば血行をよくするのでOK。
乳酸気を増やせば太らない。
EPAを多く摂れば太らない。
昆布や海藻類を摂ると小腹がすかない。
食事の20分前にチョコレートを食べて血糖値を上げれば、食欲を抑えられる。
・・・・・・・・・・・・・、いくらでも続きます。
何がよくて何が悪いか 実は本人が一番よく知っているんですね・・・ただ実践できないだけ。
実践しすぎるとストレスや他に負担がかかるのも想像に難くありません。
にわか博士になるよりも、適切な栄養と適度な運動と十分な睡眠。
自分自身でこの習慣を作る。
ここにつきますね。
124 酉年
酉年
新年明けましておめでとうございます。
昨年はたいへんお世話になりましてありがとうございました。
本年も皆さまがご健康で活力のある毎日を過ごせますよう日本ビーエフスタッフ一同 心よりお祈り申し上げます。
今年は酉年です。
今まで努力し積み重ねてきたことが開花するのが酉年といわれています。
お仕事や趣味、勉強、健康・・・、様々なことが実を結ぶよい一年です。
なぜ酉年はそのように考えられているのでしょうか?
酉年とビオストラス・・・・ちょっと無関係なこの2つ、実はよく似ています。
ビオストラスはご存知の通り大自然の英知「発酵」によって作られた食品です。
発酵は微生物がエネルギーを得るためにアルコールなどを作り出していく過程ですね。
貴重な時間を使い、存分な栄養を吸収しながら、満を持して登場するのがビオストラス。
抽出されたビオストラスはエネルギーが凝縮されたものになります。
酉は「ゆう」と読み、口の細い酒つぼのこと。
果物から酒を抽出するときに使われています。
そのため酉とは果実が極限まで熟した状態のこともさします。
酒熟して気があふれ、エネルギーが爆発する直前ですね。
いきおい酉年は物事が頂点まで達し、様々なことが実を結ぶ年をいうようになりました。
酉年もビオストラスも積年のエネルギーが凝縮されています。
たとえ小さなことでも「これまでやってきたんだ」という思いを胸に、エネルギーを爆発させる一年でありますように願っております。
12年に1度の大チャンス。
輝やかしい一年でありますように。
123 もう歳だからサー
「もう覚えられないよ。歳だから」 よく聞くこのセリフ。
この人、若いときには覚えがよかったんでしょうか?
サザエさんのお父さんの波平さんは54歳。
松田聖子やトンネルズの木梨憲武さんと同じです。
舘ひろしやジュディーオングさんは一回りも上の66歳。
波平さんとこれらの人たちの差って、何?
差を作り出す要因は2つ。
「本人の意識」と「周りの出来事」。
年齢はもともと記号にすぎません。
記号に意味を持たせて老化させているのは実は本人です。
「歳だから」と言霊にして自らの意識に刷り込んでいる「もう歳だ信号」は大罪です。
磯野波平さんは架空の人物ですがその時代の世相がそのような人物像を作り上げています。
適齢期、定年、孫、年金、バス無料。
これらは本人の資質とは無関係の周りの出来事です。
これら出来事を機会にガクンと能力が落ちるようなシステムは人間にはありません。
もし定年のような年齢制限がなかったとすると、真の実力社会が実現するかもしれませんね。
人はいくつになっても成長を続けることができる(東北大学川島教授)。
そのために日々やるべきことは、
- 頭を使う習慣
- からだを動かす習慣
- バランスの良い栄養を摂る習慣
- 社会とかかわり続ける習慣。
加齢を素晴らしい出来事と捉えているのはフランス人。
フランス人のように「あのように歳をとりたいの」といわれることを目標にしましょう。
まわりに影響されることなく、日々成長する努力にビオストラスはとても役に立ちます。
122 あの人丸くなった、角が取れた などと言いますが
「俺、カク。まだまだ丸くなりたくない」とウイスキー角瓶のCMがかつてありましたね。
自己主張強く角を立ててガンガン突き進むのは魅力のひとつでもあります。
人当たりが柔らかく温厚な人を「丸い」などと表現します。
おじいちゃん、おばあちゃんはどうしてあまり怒らない印象があるのでしょうか。
「年齢と共に幸福感も増える。」
こんな興味深い研究結果がカリフォルニア大学サンディエゴで発表されました。
21歳から99歳、計1500人の幸福度が測定されました。
研究によると低年齢層は幸福度が低く、年齢を重ねるほど幸福度は増えていくそうです。
これは若いうちは仕事や生活の不安、不満、将来の不安からのストレスが多いため。
歳をとるとストレスに対する回復や対処する方法も身につけてくるからだそうです。
最近「原因はストレスですね」とひとことで片付けられてしまうことが多いですね。
「くよくよ考えない。よく寝る。頑張り過ぎないようにしてください。」
言われなくてもわかっちゃいるが、できないのが現代に生きる人です。
米国のエールストレスセンターではストレスを回復できる人とできない人の違いがどこにあるかを研究発表しています。
違いは脳内の神経細胞の柔軟性にあるといいます。
実験は30人の脳内活動をスキャニングしながら、1分間に1枚1枚の写真を見せます。
前半の6枚は残虐な写真、後半の6枚は机やテーブルなどのノーマルな写真。
残虐な写真をいつまでも忘れられない人は脳内の柔軟性が足りない人。
結果としてストレスからの回復力が少ない人となります。
このグループは日ごろのストレス回復をアルコールや過度な食事、口論など 他にはけ口を求める生活習慣が多かったようです。
回復の早かったグループはストレス回復を他に求めず、脳内で処理していたようです。
こうなるには「適度な運動」と「瞑想」が有効であるとセンターの教授は結論付けています。
でも最近「キレル老人」が多いのは日本の老人の幸福度が下がってきたせいでしょうか?