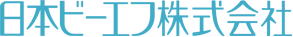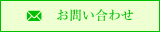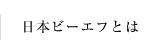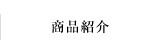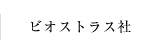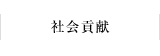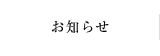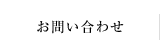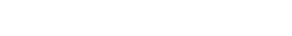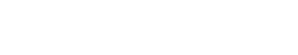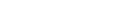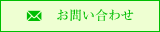138 よく、覚えているわねー。 私、最近、忘れっぽくて・・・
二人は同じ年齢なのに、この記憶力の違いはどうしておきるんでしょうか?
若いころ猛勉強してきたのでしょうか。
年をとると誰でも忘れっぽくなりますね。
しかし記憶力は脳の性質を知りうまく活用していけば向上していくようです。
ではどうやって?
人は流動知能と結晶知能という2種類の知能を備えています。
流動知能は計算スピードやパッと判断する能力でこれは残念ながら加齢と共に落ちていきます。
結晶知能は理解を深めていく能力でこれこそは日頃の行いで老化を防ぐことができるようです。
記憶力は結晶知能になります。(明治学院大学 佐藤眞一教授)
何かを記憶していくには誰でも次のような段階を経ていきます。
- 見る、聞く、体感する、などの情報入力(ストレートに脳へインプットされる)
- そのまま前頭葉に送られ印象的な順にランク付けされ低いものは記憶から遠ざかる。
- 上位ランキングされたものが海馬に送られ短期記憶となる
- 「感激した」「よかった」と口に出したり思い出したりすると長期記憶として定着する。
感激、感動した事柄は長期記憶に保存されやすくなります。
同じ体験をしているのに覚えている人と覚えていない人の違いはこの「感動」にあるようです。
ワクワクしながら物事に当たれば水滴ひとつでも記憶に定着していきます。
たとえ宇宙旅行しても感動が薄ければことごとく忘れ去ってしまうようです。
「子供ってよく覚えているわよね」とよく言われるのは子供の脳が成長段階にあることにも増して、体験することが新しいことだらけで刺激に満ちているからのようです。
大人は素晴らしい体験をしても「前と同じようだな」と感じるとそこで記憶保存が下位ランクとなりやがて忘れ去ってしまいます。
新しいことをチャレンジし、ワクワク体験しましょうとこのコラムでも何度か書いてきました。
そういうことを繰り返すと「次はこうしよう、あそこに行ってみよう」と記憶が何度も繰り返されるので定着度も増して、「よく覚えているわねー」と言われるようになるようです。
忘れっぽいと無感動は一対のようですね。
どんどんチャレンジして脳を活性化して若さを保ってください。
137 でよろしかったでしょうか
100年も続いているような美味しそうな蕎麦屋の店構え。
とても雰囲気のある重厚感を持った店の内装。
上品な器類。
陰翳礼讃とばかりな程よい照明。
心を落ち着ける柔らかで控えめな音楽。
雑誌に載っているような完璧なお店。
よくよく訊いてみるとオープンしてまだたったの1ヶ月・・・。
こういった完璧さは投資さえ惜しまなければ誰でも作れてしまうのが今の時代。
優れたデザイナーを起用すれば先月オープンのお店だって100年の老舗になってしまう。
しかし雰囲気は作っても一朝一夕に作れないものがあります。
それは「味」と「人」。
格式の高さを醸し出していくためにはそれ相当の歳月を必要とします。
このような老舗風のお店で「で、よろしかったでしょうか」は、ない。
お店を実行していく人の感性がお店をデザインした人の感性と一致していない。
レトルトフードのような味付けもいただけない。
お店とは本来オーナーの「こんな料理を作りたいっ」といった思いで創り上げていくもの。
「この場所でこんなお客様に食べてもらいたい」と生まれるべくしてその地に誕生する。
最近は発想がこれと逆になり企業のようにマーケティング先行となっているのが目に付く。
ここにこれだけこのような人が集まるからこれを提供すればこれだけ儲かる。
同じ手法でチェーン展開すれば儲けも倍増していく。
商売なので仕方ないが、店のちぐはぐさやオーナーの思い入れを感じ取れる感性を持ったお客様こそがお店の味も人も成長させていきます。
世界的建築家の安藤忠雄氏が「感性の成長は17歳まで」と言いました。
その後は絵画や音楽や映画や風景、と良いものに触れ五感を刺激して感動し、培った感性を保ち続けていく努力を怠らないように日々を過ごしていくことが大事です、と。
感性や感というのは思っている以上に老化しないものです。
毎日、たとえ些細なものでも感動し刺激と共に生きていくことが大切ですね。
136 4年後を目指して
日本中に多くの感動を与えた平昌オリンピックも無事閉会しました。
0.1秒や1cmを競うスポーツ選手の競技中のストレスとそれに対処する能力・・・。
TVを見ている私たちの想像を超える世界があります。
60kmで走っている自動車の窓から顔を出したときの風圧を想像してみてください。
スピードスケート選手の時速は約60kmで体が受けるその風速は約14mにもなります。
取り付け不完全な看板やトタン板が飛び始め、まともに立っていられなくなる強さです。
3人で滑るスピードスケート(パシュート)は後続の2人がその風圧を極力受けないようにするために60kmのスピードの中でピッタリとくっついて一直線に滑る技術が必要です。
そのための戦略や戦術が練られ、コミュニケーション作りのために日本選手は年間300日も寝食を共にしたようです。
大和の国、協調の国といわれる日本人だからこそなせる業ではないでしょうか。
多くの日本人選手が「おかげさま」と「感謝」を口にしていました。
かつて水泳の北島康介選手は総合コーチ、ドクター、栄養士、メンタル・フィジカルトレーナーと5名のコアなチームで構成されていました。
今回の選手たちにも多くの協力者やサポーターがいます。
空気抵抗を減らすために指でつまむことすらできないほど体にフィットしたスーツ。
体の延長のような靴やブーツの開発力。
絶え間ない繰り返しと協力があってこそ出てきた結果ですね。
2年前のリオ・オリンピックでは国別のメダル獲得順位と国民総生産順位がほぼ同じでした。
優秀な選手に育て上げるためには相当な投資が必要というわかりやすい数値でした。
少々残念な気もいたしますね・・・。
しかし、何にも増して言えるのは選手達の集中力、継続力、忍耐力、精神力そしてそれを培っていくための毎日の努力にほかなりません。
スポーツ選手のように目標を1点に絞り込むことが難しいのが私たちの日常です。
ある時期、現在の行動や習慣が4年後に有効か無駄かを考えてみるのもよいかもしれません。
精神の集中にもビオストラス。
スイスオリンピック委員会も推薦していました。
135 おまえ、血の巡り悪いナァ
ちょっとボーッとしている人に悪態を付くときに使われるセリフですね。
頭に血液が行き届かないと物事に対する機転が利かなくなってしまうのでしょうか。
足が冷えて、浮腫んで、逆に目が血走って・・・。
血の巡り・・・、いわゆる血流は思っている以上に重要な役割を担っています。
血管を道路に例えると血液は間断なく走り続けるトラック。
トラックは栄養素や酸素を積み、全身に届けかつ老廃した廃品を回収しながら走り続けます。
途中には突如紛れ込んだ細菌がいる場合もありますが、細菌が全身に広がっていく前に「免疫」という名のドライバーが適切に処理し回収します。
このトラックは自走できず、心臓のぎゅっと送り出すパワーで走り続けます。
いくら高機能なトラックでも走り続けなくては意味がありません。
困難なく走り続けてもらうためには整備された走りやすい道路が必要です。
重量物や危険物のような質の悪い栄養を常時運んでいると道路が傷み渋滞が始まります。
渋滞が始まると雪の東京のように様々な機能に支障をきたし始めます。
トラックは上り線(動脈)と下り線(静脈)、県道(毛細血管)などを経て心臓に戻ってきます。
その速度は上り線で最大時速約2200kmにもなり、距離は全部で地球2周半(約10万km)。
心臓より高い脳に上る時や足から帰る時は送り出す心臓にとりとてもハードな仕事になります。
これを助けるために「筋肉ポンプ」という仕組みがあります。
「ふくらはぎは第2の心臓」と言われますが歩くことでふくらはぎがポンプの役割果たします。
長い帰り道をぎゅっと押して心臓の仕事を助けます。
からだを動かさないと筋肉ポンプが機能しませんのでここでもゆるい渋滞が始まります。
それが冷え性を作り、エコノミークラス症候群になったりします。
渋滞を緩和させるために針を打ったり、マッサージをしたりしますね。
渋滞から通行止めになってしまうと心筋梗塞のような重病となってしまいます。
ビオストラスは良質な栄養素であり良質な栄養素を選別する機能を持つ小腸をも活性化します。
そしてさらに名ドライバーである「免疫」の力をさらに強化させ自己防衛力を高めます。
寒い季節ですが、からだを動かし、暖め、筋肉ポンプを大いに活用して、全身の血の巡りがよどみなく循環するようがんばり、渋滞にならないよう日々工夫しましょう。
134 戌年
新年明けましておめでとうございます。
昨年はたいへんお世話になりましてありがとうございました。
本年も皆さまがご健康で活力のある毎日を過ごせますよう、
日本ビーエフスタッフ一同 心よりお祈り申し上げます。
今年は戌年です。
蛇や猪や龍のような強面な動物と違いやさしい印象を放っているのが「犬」ですね。
犬は最も古いペットとして人と深い関係を築いて参りました。
3万5千年前の住居遺跡から家畜として犬と共存していたことがうかがえたようです。
「戌」は忠誠,献身、保護、安全といった人とのかかわりに関することが象徴とされています。
そのため戌年生まれの人は忠誠心に厚く社会性に富むといわれています。
人と犬の関係を描いた物語や逸話はたくさんありますね。
名犬ラッシー、フランダースの犬、101匹ワンちゃん、名犬リンチンチン、忠犬ハチ公、
警察犬きなこ・・・、映画の主役になったり、ヒーローの引き立て役になったりと大活躍。
犬の表情やしぐさは人の心を和ませ、ドッグセラピーという言葉も生まれています。
「戌」という字は「滅」が語源のようであまりよくない意味にとられがちです。
滅は酉年で実った作物を収穫した後の枯れ始めた状態をさしているようです。
しかし戌には収穫した作物や熟成した酒をひとつにまとめるといった意味もあるようです。
昨年の酉年は物事が頂点まで達し、様々なことが実を結び始め実現し始める年でした。
凝縮されたエネルギーが開花し始めた年です。
そのエネルギーを出し切らずに今年はそれを栄養分として体内に蓄えていってください。
蓄えながら社会と数多く関わりを持つ年にするのが理想的です。
来年は猪となって突進していきますのでそのためのエネルギー源となります。
今年も適切な栄養と睡眠と運動を心がけ、楽しく和やかに社会と関わってください。
ビオストラスを摂り続けている皆様には積年のエネルギーが凝縮されています。
それを実感できるのが戌年です。
133 Yes,Virginia,There Is A Santa Claus
これは25年にわたり繰り返し掲載された最も有名で愛された社説のタイトル。
クリスマスにはお孫さんやお子様にプレゼントの計画をしている方も多いと思います。
サンタさんの存在を心から信じている幼児達。
入学後くらいから入れ知恵(?)もあり、「いない」と確信を持っていきますね。
ある8歳の女の子が学校で「サンタなんかいないよ」と友達に言われショックを受けました。
真意をただそうと家に帰って聞くと「新聞社に投稿して訊いてごらん。」とお父様。
バージニアは言われたとおりニューヨークの新聞社「ザ・サン」に投稿しました。
なんとザ・サン紙は社説を使って返事をし、発表されるやいなや大反響をよびました。
いつも追い立てられているような最近の子供達にこんなことを語ると楽しいのでは。
-――以下社説より 1/5程に省略-――
バージニア、君の友達は間違っているよ
君の大切な友達たちは疑いだらけの世の中から悪い影響を与えられているんだよ。
真実や知恵を見通す神様と比べたらみんなのいる世界はものすごくちっちゃいんだ。
人の知恵なんて小さすぎて比べ物にならないよ。
バージニア、サンタはいるんだよ。
愛やひたむきな心があるのと同じくらい確かなことだ。
サンタがいなくなったら子供のように一生懸命信じる心もなくなって、つらい気持ちを楽にしてくれる夢のような物語もないことになってしまう。
本当に大切なことは子供でも大人でも目で見ることができないんだ。
だからすべてがわかったり見えたりするわけじゃあないんだ。
この目に見えない世界はいつも秘密のベールがかかっていて世界中の力持ちが集まったってこのベールを引きちぎることはできない。
信じる心、想像の翼,詩、愛、夢こういうものだけがベールを開いてその向こうにある気高く美しいものを映し出すんだ。
そうさ、バージニア、サンタクロースはいる。
この世でこれほど確かで永遠のものはないよ。
一万年が10回繰り返す遠い未来の先までも子供達の心を喜びでいっぱいにし続けるよ。
こういうことを社説に掲載し、喝采を浴びるところがいかにもアメリカらしいですね。
ケーキを前にしてお子さんやお孫さんにゆっくりとお話されてみてはいかがですか。
心のあり方、それが最も大きな力を作り出すんだよ、と。
132 天才少年
将棋、ピアノ、ゴルフ、卓球、体操・・・若い人たちの活躍が目立っていますね。
彼らは幼少からその能力を発揮し、天才少年、少女と呼ばれることもあります。
周りの人たちは「持って生まれたもの」と言い、自分には到達しない世界と驚嘆します。
「それは違うぞ、それはできないあなたの自己弁護だ」と言う説があります。
チャレンジしそれが簡単にできないと「自分には才能がない」と結論付け、追求しなくなる。
「才能がない」というのは自他共に納得させるための言い訳である、と。
新しいことを習熟するためには集中した10,000時間のトレーニングが必要と言われます。
一日5時間のトレーニングでも5年半必要になります。
そこでやっと人並みを超えたレベルでしょうか。
活躍している若者たちは人知れず努力を重ねながら薄皮を剥ぐように成長していくようです。
有名な音楽家を輩出するベルリン音楽学校で興味深い研究が行われました。
なぜ特定のバイオリニストたちが他より素晴らしく成長していくのか。
研究は学生たちを3つのグループ、「国際的に活躍しそうな最高のバイオリニスト」、「大変上手なバイオリニスト」、「一般的なバイオリニスト」に分け行われました。
それぞれ音楽活動時間、練習時間、活動の自己評価表、楽しさの度合いなどの膨大なデータが集められ分析されました。
学生たちは皆ほぼ8歳でバイオリンを始め15歳で音楽家になることを決意しています。
驚かされたのは日々の音楽活動に関する時間(個人レッスン、グループレッスン、独習、音楽の授業など)を総合するとそれぞれのグループに差がなく週51時間とほぼ同じことでした。
実力の差はどこでついていくのでしょうか?
大きな差となって表れたのは「一人での練習時間・・・独習」にありました。
もっともつらく単調で地道で面白みに欠ける独習を黙々と続けている。
それを多くは体力気力のもっともある朝か午後の早い時間に行っているようです。
「一般的グループ」は独習時間が少なく疲れていると感じる遅い午後に集中していたようです。
安易に「天才」と呼ぶのは失礼で、子供達の将来を考えると慎重な言葉選びが望まれます。
国際的なプロフェッショナルでなくとも地道な努力は大切ですね。
単調な行動が楽しみに変わると、それが脳の活性化となり老化防止につながっていきます。
131 バイリンガルBaby
ゴクミこと後藤久美子さんは元祖美少女ですね。
フランス人の元F1レーサー ジャン・アレジ氏と結婚し、現在スイスで暮らしています。
長女エレナ・アレジさん(20歳)はフランス語、英語、日本語など6ヶ国語が堪能だという。
「魅せられて」のヒットで有名な台湾出身歌手のジュディーオングさんは日本語を母国語のように話しますね。
5ヶ国語に精通し、あんなに流暢な日本語なのにそれでも3番目に得意だといいます。
タレントのLilicoさんも癖のまったくない日本語を話し、5ヶ国語を話すそうです。
スウェーデンで育ち子供のころは様々な国の子供たちと普通に遊んでいたようです。
こんなにも多くの言語を話し、頭の中が混乱しないのでしょうか。
数ヶ国語を操れると脳にどんな影響があるのでしょうか?
米国のプリンストン大学で24人の生後20ヶ月の幼児を対象に実験が行われました。
まだまともにお話もできない年齢ですね。
幼児らが普段聞いている言語は父のフランス語と母の英語(あるいは逆)です。
その結果、幼児らはフランス語と英語を無意識に分類できたといいます。
例えば日本語の犬にあたる英語のドッグ、フランス語のチーンを聞かせたとします。
これらの言葉をはじめて聞いたとき、違った意味を持つ単語としてではなく、異なった言語にそれぞれ属するということを理解できていると言っています。
このすばらしい脳のメカニズムはまだ解明されていないようです。
しかしルイス・ウイリアム博士は家庭内で話す言語が複数あるだけで子供の様々な問題解決スキルや記憶能力を改善することが将来できると言っています。
脳の前頭前野と前頭皮質が刺激されより良く発達していくようです。
日ごろいくつかの言語を同時に聞かせることへのマイナスは無いと言っています。
東京オリンピックも3年を切り、そのせいか英語を習うご高齢者も増えているようですね。
2つの言語の訓練からくる恩恵はどうやら赤ちゃんだけのものではないようです。
他国語の訓練は認知刺激として機能するので老化の進行から保護するともいっています。
新しいことを楽しく続けることは体内の様々なところに良い刺激を与えてくれますよね。
脳はもちろんのこと、そのワクワク感は免疫力をも高めてくれます。
130 未来ではなく近い将来
今の10歳の子供たちが将来仕事に就く頃・・・。
7割の子供が今この世の中に存在していない職業に就くと言われています。
たしかに今人気のユーチューバーやプロゲーマーなどの職業は数年前にはありませんでしたね。
また90%以上の確率でAIに変わってしまうだろうと言われる職業があります。
銀行窓口係、経理事務員、保険事務員、驚くべきところではプラント技術設計者、測量士、弁理士、翻訳者、細菌学研究者、税理士など計31業種。
70%まで確率を下げると物理学者や工学技術研究者、刑務官まで(週間ダイアモンド調査)。
将棋やチェス、囲碁までAIに負けてしまいました。
それどころか藤井聡太4段の対戦解説では「AIなら次の一手はどのように打つ?」とAIの戦法がお手本になってしまっていますからもうその存在を認めざるを得ません。
でも、「まさか人間の内面的なところまではこないだろう・・」、と思っていると、
Woebot(ウォーボット)というコンピュータープログラムが頭角を現しはじめました。
欝や気落ちしている患者のためのシステムです。
コンピューターの問いかけに対して患者が一問一問応えます。
膨大なデータから患者にとって最適な質問を繰り返し、時には最適な画像を添えます。
状況にあった音楽を聴かせ患者の気持ちを和らげ、回復させていきます。
インターネットを通し毎日決められた時間にやりとりするというプログラムです。
米国スタンフォード大学では2つのグループで2週間その効果を実験しました。
不安を取り除き平常心を作ることに非常に効果があったという結果が出ました。
幼い頃から受験一辺倒で人間的魅力の欠けるお医者さんが多くなっている昨今です。
むしろAIの方がより信頼を置け、人間味(?)にあふれているかもしれませんね。
自宅にいながらできるので不登校児や自閉症にも効果が見込めそうです。
「呆けは神様の贈り物」と言います。
しかし働かなければ生きていけなくなるこれからの時代です。
そんな悠長な言葉は通用しないかもしれません。
「健康でAIにできない仕事ができる」 これが次代のキーワードでしょうか。
129 アルツハイマーじゃないよ
- 効果があるかどうか疑問に思った薬はおそらく無効である。
- 投薬を中止して患者の状態が悪くなる様な薬はほとんどない。
これは医師のバイブルといわれている「ドクタ-ズルール425」の一文
私たちは認知症の事をアルツハイマーとひと言でかたづけてしまいがちです。
しかし認知症には大きく分けて3タイプあるようです。
アルツハイマー症 忘れっぽい、穏やか、いわゆる可愛らしいお爺ちゃん、お婆ちゃんタイプ
ピック症 記憶は良い、すぐ怒る、行動異常がある
レビー症 元気ない、鬱、幻覚を見る、寝言が多い
もっとも大切なことは患者がどのタイプに属しているかを医師が見極める事。
見極められずに投与すると、例えばすぐ怒る患者(ピック症)に元気になる薬(レビー症)を投与したら・・・、結果は明らかですね。
医師の誤った判断からこのような投与が行われている事が多いのには驚かされます。
それがわかるのはある期間の投与が行われた結果を見ての事。
ただただ信じて摂り続ける無抵抗の私たちはたまったものではありません。
「ひと目みただけでどの認知症タイプかわかる事も多い。」
「他院で投与された薬を半分にするだけで改善する事も多い。」
「薬を変えることによって車椅子だった患者が歩けるようになった。」
日本ビーエフの勉強会では市川フォレストクリニック 松野院長がこうお話されていました。
このような医師が増えていく事が健康寿命を延ばしていくことになると思います。
加齢と共に脳機能が衰えていくのはしかたがないこと。
それはしわが増えたり、運動機能が衰えたりすることと同じ事。
しかし薬による悪化からは絶対に避けたいものです。
- 患者には病人になる方法を教えるのではなく、健康になる方法を教えなさい。
こんな文もドクターズルールでは教示しています。