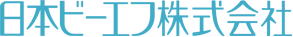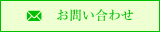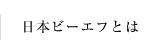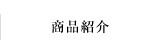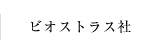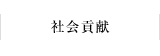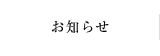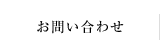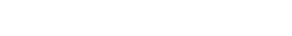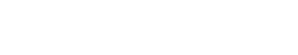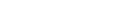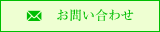158 子 年
新年明けましておめでとうございます。
昨年はたいへんお世話になりましてありがとうございました。
本年も皆さまがご健康で活力のある毎日を過ごせますよう、
日本ビーエフスタッフ一同 心よりお祈り申し上げます。
今年は子年です。
子年は十二支の先頭にあり新しい物事や運気のはじまりにあるといわれます。
子の刻は午前0時、一日のはじまりでもあります。
はじまりにはいつも「こうしたいな」という欲求が伴います。
昨年のノーベル化学賞の吉野彰博士の研究心のはじまりは「ろうそくの科学」
日常の何気ないことを「知りたい」という欲求が4年生のこども心を掻き立てました。
「欲深い」という言葉がありますが、ここから連想されるのは、
欲深い王様、欲深い商人、欲深い継母・・・良い人にはあまり形容しない言葉ですね。
自分のものにしてしまいたいと欲し、手に入れよう、奪おう と利己的なイメージがあります。
しかし欲というのは物事を向上させる原動力です。
欲のないところに成長や発展はありません。
欲の強さが続ける根気を生み出します。
幼児は早く周りのことを知りたいという欲から動き回り、手にとり、口に入れます。
子供の成長は「知りたい」という欲求がなければ飛躍的な成長はありません。
「欲しい」が「こうしたい」から「こうすればいい」を引っ張り出していきます。
欲のないまま勉強を強いてもその知識が独創的に広がっていくことは少ないかもしれません。
子供の欲は抑えるのではなくコントロールしてあげることが大事なようです。
分別ある大人の皆様は欲をコントロールする術を心得ていることと思います。
でも今年は大いに欲深さを発揮してみませんか。
こまめに動き、いろいろなことに首を突っ込み、何でもかじり、そして適応する。
そんなねずみのような行動が運気を呼び込むはじまりになるかもしれません。
大変革の年といわれる2020年。すばらしい一年となりますように。
157 お正月には○○して
フーテンの寅さん「男はつらいよ」が年末に封切りされます。
「サザエさん」の実写版ドラマが天海祐希さん主演で放送されましたね。
日本の職人さん達の目を見張る手仕事が最近よくTVで紹介されます。
「Youは何しにNIPPONへ来ましたか?」と旅行者へ問いかける番組があります。
「NIPPONで○○を学びたい」という人を招待して夢をかなえてあげる番組があります。
最近、単なる郷愁ではなく古き良き日本を紹介する番組も増えました。
昭和を知らない若い人たちが「昭和の雰囲気っていいね」と言います。
日本をあらためて見つめなおす・・・こんな風潮が年々高まっています。
昭和20年日本は焦土となり壊滅状態となりました。
武力で負けたのですが当時の日本人は文化まで劣っていると感じてしまいました。
はじめて見る西洋人たちの華やかさに驚き、憧れました。
米国人のライフスタイル、女性の美しさ、ジープ、チョコレート、ジャズ・・・。
追いつかなくてはと伝統的価値より経済を重んじ100年は立ち直れないと言われていたのにあっという間に経済成長をなしとげ、この小さな国が世界第2位の経済立国にまでなりました。
ふと気がつくと大切な物が経済成長と引き換えになくなっていました。
長い歴史の中で育まれてきた日本独特の文化、風習、気質、風景・・・。
10数年くらい前からそれを取り戻さなくてはと多くの日本人が思い始めました。
歴史ある日本の文化がわずか200数十年の米国に劣るはずがないと気がつき始めました。
SNSで知り合い軟禁されていたという子供達の事件が相次いでいます。
警察が踏み込んだときには携帯を持ち、机に向かって勉強をしていたと言います。
この中学生は我が家より知らない人の家に安住を求めています。
子供にとって家が安らぎの場所でなかったら健全な精神はどこで育っていくんでしょうか。
日本の風習を感じることができる「お正月」はもうすぐです。
凧揚げよりネットのほうが刺激はありますがその代償を考えてあげるべきは大人ですね。
インターネット依存症の外来もできたようですが、依存症は麻薬に近い症状が出るようです。
お正月は古きよき風習に浸りながら「子供たちの健全」を考えてみるよい機会かもしれません。
156 ふたつの世界
親友なんて必要ないでしょう。
彼女はいらない、わずらわしいから。アイドルだけでいい。アニメのアイドルは最高。
恋愛は楽しみのためにする。結婚して子供を持っても社会が助けてくれないでしょ。
しゃべらなくたってゲームを何時間もできればいいよ と同級生が帰っていく。
小学校の運動会ってみんなが同じことをやって・・・、なんでアレ必要なの、協調性?社会性?
いちいち電話するな。ラインがあるでしょうが。でも返信がないと怒る。無視する。いじめる。
働くの嫌だ、家にいたい。・・・・・・・あきらかにこれまでと違った人種がいますね。
でもインターネットが無かった世代が、「人として間違っているぞ」とは軽々しく言えません。
日本中をこれまでない感動に包み込んだラグビーワールドカップ。
この大会を通じてはじめて知った言葉の1位がなんと 「トライ」。
それほど無知だった日本人の心をつかんだのは日本代表選手たちの闘魂と団結力。
ラグビーのような激しく当たるスポーツにまずに必要なものは「体力」。
これまで体力で劣っていた日本チームでしたが、年間250日間の合宿で作り上げてきた代表選手たちの体力は外国人選手と比べても決して見劣りしませんでした。
そしてone for all, all for one 一人は皆のために、皆は一人のために、の「協調性」。
「和」を尊んできた日本人には協調性はお家芸。
体力を手に入れた日本チームは今後ますます強くなっていくことが期待できますね。
人との直接的な交わりを避けている風潮と熱いつながりを求め合うこの2つの相反する世界。
どちらがより人間として大切で必要かは明確です。
しかしこれを良し悪しで判断し人と接するとイライラが募りパニックになるかもしれません。
世界が2つあってそれぞれの住人が行き来していると考えるほうが無難かもしれませんね。
そこでも人が育ち、新しいコミュニティーもすでにできつつありますからね。
古い世界にいる私達が若い頭脳を保つためにも違う世界にも足を踏み入れる必要があります。
「人生100年時代」はいつまでも社会と関わり合うように求められています。
選手でなくとも体力と協調性は最重要項目。
体力は睡眠、運動、栄養。協調性は柔軟な思考。
ビオストラスで体力をつけエイジブロッカーで柔軟にし、違う世界を行き来してみましょうか。
155 年齢は数字
「年齢は気にしない。もうそういう時代よね!」
67歳の女優、夏木マリさんはCMの中で誇らしげにそう言っています。
「なんかワクワクしますね」と若いモデルが応えます。
年齢を重ねるごとに新たな魅力を作っていく彼女ならではのセリフですね。
「そういう時代」ってどういう時代でしょうか?
歳を重ねていくワクワク感って何でしょうか?
時代を読んだこのフレーズは現代こそ最も旬なフレーズのようです。
「そういう時代」とは、年齢は数字に過ぎないと自他共に認めはじめた時代。
ワクワクとは心躍る期待感で今にも動きたくなるような気持ち・・・でしょうか。
「(歳のわりに)記憶力がいいね、(歳のわりに)よく動くな、歳のわりに・・・・etc」
人を評する時にこんな言い方をすることがありますね。
でもこれはあくまでもその人の年齢を基準として言っているに過ぎません。
この年齢だったら普通はできないはずなのにできている・・・(だから)すごいネェ・・・と。
それをほめ言葉として捉えていたとしたらそれはもう引退を受け入れた人・・・。
様々な人たちの活躍で、評価に年齢が取り払われつつあります。
定年制は企業や社会が規律を作るための決め事で、人の能力に定年はありません。
これまで培ってきた知識、経験、人脈全てを投じて自分しかできないことを提供する。
小学生と大学生と80歳の人が集まってひとつの仕事をし、解散しまたどこかで集まる。
小学生だからといって子ども扱いせず、「年寄りの冷や水」などと見ず、能力だけを見る。
「そういう時代」はいかにも楽しそうで素晴らしくもウカウカと隠居していられない厳しい時代でもあるようです。
脳科学者 池谷裕二氏によると、脳は鍛えれば記憶力は増すという。
脳は衰えの遅い細胞で70歳を超えても向上し、記憶の蓄えが創造力に繋がっていくという。
記憶力が落ちたと言うのは自己暗示で情熱や感動が薄れていくとそう感じてしまうらしい。
大切なのは「やってみようか」という行動力とそれに伴うワクワクとするような心のあり方。
「歳を考えてみろよ」なんていうセリフ自体がなくなるかもしれませんね。
154 子供叱るな来た道だもの、年寄り笑うな行く道だもの
これまでの人生とこれからの人生を深く考えさせられてしまいます。
誰もが必ず経験する未知の世界・・・「老い」。
でもほとんどの人が備えをもたない「老い」。
備えないのはまだまだ不要と思っているからでしょうか。
しかたがないとあきらめているからでしょうか。
老いと共に少なからずついてくる「呆け」。
さらに多くの人に迷惑をかける可能性のある認知症。
2025年には700万人の認知症患者がいるだろうと言われます。
(そのときの高齢者人口は3500万人と推計されています)
誰もが恐怖心を持ちながら何をやったらよいのかわからないのが現実ですね。
しかし認知症の1/3は予防可能といううれしい説があります。
認知症はまず以下の生活習慣(病)を少しでも改善することをしつつ、
・高血圧 ・肥満 ・2型糖尿病 ・喫煙 ・鬱 ・運動不足 ・社会的孤立
・中年期の聴力低下 ・中等教育の未修了者
以下の7つの習慣が予防に効果的といわれています。
1適切な有酸素運動 筋トレ 2料理 3歯磨き(歯を大切にする)
4音楽 5絵を描く 6脳トレ 7よい睡眠
筋肉と脳は常に連絡を取り合っているため筋トレは脳の情報伝達能力を向上するようです。
そして有酸素運動は血流を促進させます。
音楽、料理、脳トレは楽しみながら常に新しい情報に触れるためとても効果的です。
咀嚼運動は脳によい刺激を与えます。
適切な入れ歯を作った結果認知症が改善された実例はたくさんあります。
脳には不純物が溜まりやすくこれを除去するのがよい睡眠です。
血流促進は健康の基本ですが認知症にも効果的です。
日本ビーエフのエイジブロッカーは血流促進に欠かせない3つの物質で構成されています。
7つの習慣とともにぜひお試しください
153 私も苦しんだ
物事、そう簡単に成し遂げられるわけありませんね。
しかし「エッそんな簡単なら」とつい乗ってしまいがちなプロの販促テクニック。
インターネットの使用で 以前にも増して横行しています。
エモーショナルマーケティングとはこんな順序で行われます。
- お客様の悩みを知る。
- このままほおって置くとますます状況が悪くなっていくと不安を煽る。
- 最近はここで、「実は自分も過去同じことで悩み、苦しんでいた」のフレーズが入ります。この人ならわかってくれると急に親近感がわき、信憑性も生まれてきます。
- こんなつらい悩みもこれを使用すれば(この手法を実施すれば)短期間で解決できます。と援助の手を差し伸べ、商品や手法のセールスをはじめます。
- 「しかし限定です」と誰もが買えるわけではないことを伝え、手に入らないことを残念がらせ何とかして手に入らないかと思わせる。あるいは販売期間を設定して急がせる。
かつては、「つらい癌が治った」などといって健康食品業界にも横行していました。
人の身体に直接影響を与えますから国も薬事法という法律で排除に乗り出しました。
現在は「悩み」の代わりに希望や夢などが対象になったりします。
ここには国の規制が入りにくいようです。
英会話熱も格好のターゲットです。
「もうあの辛い暗記や難解な文法も要りません」
ちょっと考えるとそんなわけないことは誰にでもわかることですね。
・高血圧は毎日たったこれだけで改善
・ゴルフは○○するだけで上達
・ギターの上達にお悩みの方へ
・何をしても治らなかった腰痛がみるみるうちに
企業が行っていたマーケティングを個人がネット上で行っているのでたちが悪いですね。
新しいことを習熟するためには集中した10,000時間のトレーニングが必要と言われます。
一日5時間のトレーニングでも5年半必要になります。
先の目標に向かって毎日励むことは生活にハリが出て若返りにもなります。
目の前のハードルを越えるよりつい近道で楽にゴールに行きたくなってしまうのが人の常です。
でも「そんなわきゃないだろう」とすべての広告は疑ってみることが必要かもしれませんね。
152 そんなにたくさん?
他の科からはこの薬も摂るように言われているんですが、一緒に摂って問題ありませんか?
分厚い文献を見てドクターは・・・、「大丈夫でしょう。」
私達は信じるしかありませんね。
薬を4剤以上飲み続けている患者は医学の知識が及ばない危険な状態にある。
これはドクターズルール425 医師の心得集にある言葉。
「あらっ、私は?」と思っている方も多いのではないでしょうか
老年専門医のマーク・ビアーズ博士の「ビーアースリスト」というものがあります。
これは「併用すると不適切な薬」のリストです。
高齢者が併用しやすい薬、降圧剤や睡眠薬、抗不安薬も挙がっています。
日本は特に抗不安薬の処方がダントツに多い。
転倒やせん妄のリスクが高いのに一般的なためいまだに投与されています。
それぞれの薬は国の厳しい規定で管理されています。
しかし2種類が掛け合わされ、3種類、4種類になるとその結果は理解の範囲を超えます。
そこに各個人の体質が加わると「医学の知識が及ばない危険な状態」は明らかですね。
病院の収入は診療報酬と国からの研究費の獲得。
良い人材を獲得し、良い研究を続け、良い治療をするには多くの資金が必要になります。
日本には医療にかかるお金が点数制で決まる診療報酬制度というものがあります。
科によって点数の分配が異なり、内科、外科の治療は高得点となり収益アップに繋がります。
「血圧は90+年齢で大丈夫」と言うドクターと「120台」と言うドクターがいます。
この違いは、その後の責任を誰が負うかというもの。
降圧剤を摂れば当面の高血圧による発症リスク、例えば心筋梗塞などは下げることができます。
しかし薬を摂りつづけたあとの将来にも例えばせん妄などリスクはあります。
でもそれはドクターの責任でもないので処方して近々のリスクを減らしたほうが賢明ですね。
ネットの氾濫でドクターよりも患者のほうが調べつくし詳しいことさえあります。
大切なのは調べつくしたあとの日常の過ごし方です。
免疫力を高める努力をし、自ら健康生活を送っていくことが大切ですね。
151 この歳にもかかわらず
ビートたけし氏が言いました。
「痛いっ というのは大切でサー、からだを制御するためのものなんだ。
もし痛みが無かったらみんな知らないうちに無理して死んじゃうかもしんないよ。」
たしかに痛みは限界を告知してくれるものですね。
「しばらく安静にして回復を待て」 という身体からの正確なメッセージですね。
痛み、恐れ、それを堪える能力を人は成長しながら学んでいきます。
幼児は痛い経験をして、はじめてやらないほうがよいことを覚えていきますね。
怖いけどちょっとやってみた。
でも失敗して痛い目にあってしまった。
その経験を基にまたチャレンジする。
この適度な恐れや痛みの向こう側だけしか上達や成長はないのかもしれません。
痛いにもかかわらず やり遂げたよ。
この「にもかかわらず」という言葉を大切に考えたい。
諏訪中央病院名誉院長で多くの著書を持つ鎌田實先生はTV番組でこうおっしゃいました。
重病だったにもかかわらず健康な毎日を過ごせるようになったんだ。
危険と言われたにもかかわらずやり通したよ。
親戚中にやめろといわれたにもかかわらず続けたよ。大成功だった。
「これは良くない状況を好転したときに使える力強い言葉なんだよ。」
この言葉には様々な恐怖を克服した努力のあとが見て取れますね。
「年齢というのは単なる数字に過ぎない。」と言う人がいます。
しかし数字の大小にかかわらず、この数字はとても強い魔力を持ちます。
「どうせ・・・」という自己暗示を潜在能力に刷り込み勝手に限界を作ってしまう魔力です。
60歳になると定年という社会が作り上げた限界説に潜在意識が勝手に応え、活力が失せていくように仕向けられてしまいます。
悪い状況に対しては「にもかかわらず」で立ち向かうと好転しそうですね。
人生100年時代、少しだけ恐れや痛みを伴いながら活力ある毎日を過ごしましょう。
150 次へ
令 和 という新時代を迎えました。
平成の30年間は戦争のない平和な時代でした。
「日本人は平和と水はただで手に入ると考えている。」と他国から揶揄されていました。
島国ゆえの「平和ボケ」「ぬるま湯」とも言われていました。
しかし戦争の脅威を感ずることなく、平和に暮らせたのは先人達の努力や犠牲のおかげ。
感謝を胸に、令和も平和が続くことを願います。
東京大学入学式の上野千鶴子教授のスピーチが話題になっています。
難関を乗り越えて鼻高々で意気揚々として臨んだ新入学生たちに向かって、
「頑張って報われたのは努力の成果ではありません。環境のおかげです」
「励まして、手を持って引き上げてくれたから。」
本人の大変な努力は認めています。
しかし勉強に専念できたのは周りがお膳立てしてくれたおかげ、と言い切りました。
学校や塾の先生の暖かいまなざし、親の収入、専念できる時間・・・、すべては周りの気配り。
ましてや政情不安があったら勉強どころではありませんね。
ひとつのことに集中し技能を高めていけば生きていくことができた平成という時代。
対して令和となったこれからは予測不能な未知の世界。
正解の無い世界となっていきます。
東大というブランドの通用しない世界でも生きていける知恵を身につけて欲しい。
こんな段階で満足せず次のステップに上がれという力強いメッセージが込められていました。
これまで誰も見たことのない智を生み出す智を育くめ、と
高齢社会となり超高齢化に進みつつある日本、多くの人たちが老いに不安を抱いています。
成人病よりも、多大な迷惑をかけるであろう認知症には誰もが大きな脅威を感じています。
日頃何をしておけばよいのか、何をすれば防げるのか、それこそ正解のない世界。
日本ビーエフは認知機能という新しい分野にチャレンジしています。
そんな中、あらためて感じるのは基本となる健康なからだと、健全な精神。
世界のビオストラスと新サプリメントの相乗効果を楽しみにしてください。
149 ミスチルと山口素堂
♪♪ ありふれた時間が愛しく思えたら それは愛の仕業と小さく笑った ♪♪
これはMr.チルドレンのヒット曲「Sign」の一節。
「ありふれた時間」とは大きな買い物をしたとか、旅行に行っているとか、素晴らしい出会いがあったなどの特別なことではありませんね。
いつも何気なく繰り返されている時をさしています。
日常とは違った特別なことをしたときに感じる「幸せ感」は人それぞれいろいろあります。
しかしこれはひとつの「刺激」であり時間とともに減少しやがて消え去ってしまうもの。
「人は欲しいものを手に入れた瞬間からそのものへの興味は半減する」
といわれるマーケティングの鉄則はそれを見事に表現していますね。
人が愛しく思える時間を感じるのは刺激からではなくほんとうに日常の何でもないこと。
些細なことや粗末なもので幸せを感じるには心の奥深さや豊かさが必要ですね。
そしてこれを続けるのは日常の努力が必要です。
目には青葉 山ホトトギス 初鰹
山口素堂のこの句は毎年繰り返される何でもない日常を詠んだ句。
今年も味わうことのできたこの時にただただ作者の満足感のこもった吐息を感じます。
最近ベビーカーにiPadをナビのように固定して散歩しているママを見かけました。
2歳くらいの幼児がベビーカーの中で人差し指で慣れた手つきで操作しています。
この子は画面の中だけに強い興味を持ち、そこから多くの刺激を得ることはできます。
しかし木々の色や風や空気や匂いや雑踏の音を自らの感性で感じとることができません。
日常の当たり前の風景よりも刺激を優先させられています。
「ムシャクシャしてやった」という最近の事件はこんなところで作られている様な気がします。
美味しいものを「おいしいっ」と感じて食べることができ、よく眠れ、よく動ける。
これを「健康」といいます。
こんな些細なことに感謝できるのは人間の特権ではないでしょうか。
AIにはできない 将来も絶対できない最高等技術ではないでしょうか。